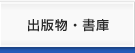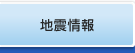書庫 > コラム
親しかった人たち、親しい人たち(1)−私の国際交流(その11−1)
東京電機大学 教授 片山 恒雄
地震工学、地震防災の分野で知り合った人は多い。すでにお亡くなりになった人もあれば、まだまだ元気で活躍している人も多い。よく顔を合わせる人もいれば、しばらく会っていない人もいる。まぁ、忘れないうちに、そんな人たちとの個人的な思い出のいくつかを書いておこうというだけのことである。ここに出た人たちを選んだ基準はまったく私的で根拠も何もない。まだまだ書いておきたい人はいるが、今回はこれくらいにしておこう。
リュウ・フイシアン先生(Liu Huixian)は中国の地震工学の父といわれる人である。先生はアメリカのブラウン大学の教授をしておられたが、中国が独立した1948年に帰国してハルビンの工程力学研究所の前身にあたる研究所に入られ、その後30年にわたって、所長を務められた。1991年に病を得て翌92年6月24日にお亡くなりになった。私がお知り合いになった頃の中国は、まだ人民服と自転車の国だった。米国暮らしが長かったから、西欧の生活をよく知っておられただろうが、いつもニコニコとそんなことは気にしないというふうだった。
リュウ先生とは何度もお会いした。その中の2回がとくに印象に残っている。このシリーズの(その3)に書いた、唐山地震の調査で訪中した際に、ハルビンで大変お世話になった。もっと個人的にお付き合いしたのは、久保慶三郎先生が東大の生産技術研究所を退官されたときの記念講演会に来ていただいたときのことだ。久保先生は1982年3月に東大を停年で退官されたが、退官記念の行事として少し変わったことをやりたかった。そこで外国からの講師に参加していただいた記念講演会を企画した。アメリカからハウスナーとペンジンの両教授、中国からリュウ先生、マケドニアからペトロフスキー教授、これに岡本舜三先生と久保先生に加わっていただいた6人の講師からなる記念講演会を企画したのである。なにしろ偉い先生方のご都合を合わせるので、講演会は退官された翌年になった。私は成功間違いなしと踏んでいたが、意外なことに、久保先生自身が、「おい、本当にみなさんが来てくれるかなぁ」と弱気になられたときもあった。講演会は大成功、たくさんの方々が会場に足を運んでくださった。
久保先生の退官と記念講演会の間に、日本海中部地震(1983年5月26日)が起きた。リュウ先生がこの地震の現場を見たいとおっしゃるのでご一緒に秋田へ出かけた。秋田まで飛行機で行き、私がレンタカーを運転して男鹿半島を一周、能代の典型的な商人宿に一泊して帰ってきた。途中で、当時基礎地盤コンサルタンツにいた安田進さん(現・東京電機大学)が液状化の現地調査をしているところを見せていただいた。中国の偉い先生が来られるのならぜひ会いたいという工業高校の校長先生が宿に来られたそうだが、このことは同道した磯山龍二さん(エイトコンサルタント)に聞くまで、すっかり忘れていた。リュウ先生はこの寅さんが泊まるような宿がひどく気に入られたようで、浴衣姿でいろいろとお話をした。お歳からしても、私にとっては父親のように思える方だった。
キンタナールさん(Roman L. Kintanar)は、1958年に若干29歳でフィリピン気象庁(PAGASA)の長官に任じられ、その後約40年の長きにわたってその職を務めた。その間1978年に、世界気象機構(WMO)の会長に推挙され、1983年まで会長職を務めている。要するに、世界の気象学の超大物である。私個人としての付き合いは、国際防災の10年(IDNDR)期間内のいくつもの会議での出会いや、WSSI、INCEDEの活動でフィリッピンを訪れた際のお付き合いである。WSSIの初期の活動やINCEDEのフィリッピンとの共同研究などをとおして、キンタナールさんとはずいぶん親しくしていただいた。
ともかく、キンタナール兄弟は(何人おられたかは忘れたが、)全員が何らかの立場でフィリッピンの上層階級の一人だったようだ。気象学者のキンタナールさんはそんなことはまるで気付かせず、いつもニコニコとされたきさくな方だった。だが、ご自宅に夕食に招かれたときのことである。塀の上に有刺鉄線が張られているのは当然として、銃を持ったガードが門を守っている。途上国の特権階級に属して生活することの怖さを目の当たりにした感じだった。貧富の差の大きさを考えれば、当然のことかもしれない。家の中に入ってびっくりしたのは、大きな家のあちこちに置かれた甕である。私の背と同じぐらいの高さの甕を見て、私ははじめて、アラビアンナイトのアラジンと40人の盗賊で、盗賊が隠れたという甕はこんなものだったのかと納得した。2007年に亡くなった後、気象学における多大な貢献に対し、火星と木星の間にある小惑星の1つに ”6636 Kintanar” の名前が残されている。
テディー・ブーン(Teddy Boen)は、インドネシアの地震工学エンジニア、中国系のインドネシア人である。「テディーを知っているか」と聞いて、「知らない」というインドネシアの地震工学の関係者がいたら、間違いなくいんちきである。いつ、最初にテディーにあったかは、もう思い出せない。30年近く前のことだったのではなかろうか。IAEEでも、WSSIでもインドネシアを代表する地震工学者として長くテディーと付き合ってきた。建築研究所の国際地震工学コースに参加したのが、地震工学との馴れ初めということもあって、大変な親日家である。テディーは耐震設計のコンサルタントとしてもつとに知られ、ジャカルタのメインストリートやヒルトンホテルの大部分の耐震設計は彼の手になるものだ。ビジネスマンとしても長けているのだが、一方、国内で発生した主な地震の被害はひとつ残らず私費で調査し、写真入りのわかりやすいレポートをつくっている。自分で十分なデータを持っているという自負もあって、官に対しては常に批判的であり、官から煙ったがられることも多いようだ。
思い出は多いが、きわめて個人にわたる話を4つほど書いておこう。
私の長女が大学卒業の旅行で友人たちとバリ島に行ったときのことだ。バリの飛行場についたら、黒塗りのリムジンのお迎えが待っていたそうだ。どうせ大学を卒業したばかりの若者の旅行だから、いわゆるパッケージ旅行でホテルもたいしたレベルのものではない。ヒルトンに泊めてあげるのにと言われて、かえって困ったらしい。2つ目はたぶん15、6年前のことだったと思う。つま先から痺れが来てそれがだんだん上ってくるという奇病にかかってしまった。そのままでは、死を待つよりない。幸い親戚がドイツでお医者さんをしていて、病状を知らせたら正しい病名がわかり、一命を取り留めた。ちょうどインドネシアで会議があり、病院にテディーを見舞ったが、病気は快方に向かいつつあった。3つ目は、WSSI のミャンマーにおける活動である。ミャンマーはインドネシアから行きやすいところにあり、テディーは何度も率先して現地での講義を行い、コンピュータプログラムの提供などをしてくれた。4つ目には、奥さまのことを書いておこうか。テディーの奥さまは日系の大手化粧品会社の副社長で、(テディーと奥さまはまったく別の財布だそうだ。うらやましい。)飛行機の中で出るおつまみがお好きというので、一度お土産にお持ちしたことがある。
テディーが官から煙ったがれていると書いたが、2004年インド洋津波の後は、国内外の機関が彼の力を借りないわけには行かなかった。私は、地震の翌年バンダ・アチェに行ったが、彼が説明する津波直後の惨状は凄まじいものだった。また、若い人たち相手のワークショップでは、聞き手たちの何度もの笑い声に彼の人間的な魅力を再確認した気がした。(この部分に関しては、当コラム欄の「バンダ・アチェはいま」もお読みいただきたい。)
フリオ・クロイワさん(Julio Kuroiwa)は、日系2世のペルー人である。1933年4月22日生まれ。建築研究所の地震工学の通常コースを1961年から1962年にかけて、さらに特別な個人コースを1975年から1976年にかけて修了した。建研の地震工学コースは1960年にスタートしたから、もっとも初期の段階に滞在されたことになる。いまはすでにペルー国立工科大学を退官されて、名誉教授の立場にある。私がつくばの防災科学技術研究所にいたときも何度か訪ねてくださった。建築研究所が母校のようなものだから、日本に来ると建築研究所に立ち寄り、すぐそばの防災科研にも挨拶にお見えいただいたのだろう。クロイワさんもたいへんな親日家であり、日本での勉強がなかったらペルーの地震工学はなかったかのようにおっしゃる。建研の通常コースと個人コースの間に、1965年から67年の2年間をカリフォルニア工科大学でポスドクとして過ごしているのだが、そのときの話を聞くことはほとんどない。あるとき、ご自分で書かれた”Disaster Reduction−Living in Harmony with Nature” という本をいただいた。クロイワさんの仕事の集大成とでもいうべき内容の本だったが、「これを日本語で出版してもらえないだろうか」というお話には当惑した。しかし、建築研究所が中心になって、「防災:自然と共生しながら」(2005年9月、建築研究振興協会)が発刊されたのを知ってホッとした。
覚えている人が多いと思うが、1996年12月17日、ペルーの首都リマの日本大使公邸で開催されていた天皇誕生日を祝うレセプションをテロリストが襲撃、占拠した事件のときである。最初は600人もいた人質も徐々に解放されたが、4か月以上たった翌年の4月22日ペルー警察の突入によって事件が解決したときにも、まだ70人ほどは残されていた。事件が解決して、人質たちがバスに乗り込むテレビ画面の中に、クロイワさんの顔があった。(つづく)
Copyright (C) 2001-2012 Japan Association for Earthquake Engineering. All Rights Reserved.